居場所がない。だから、ここにきた映画『よそ者の会』西崎羽美監督、川野邉修一さん、坂本彩音さんインタビュー


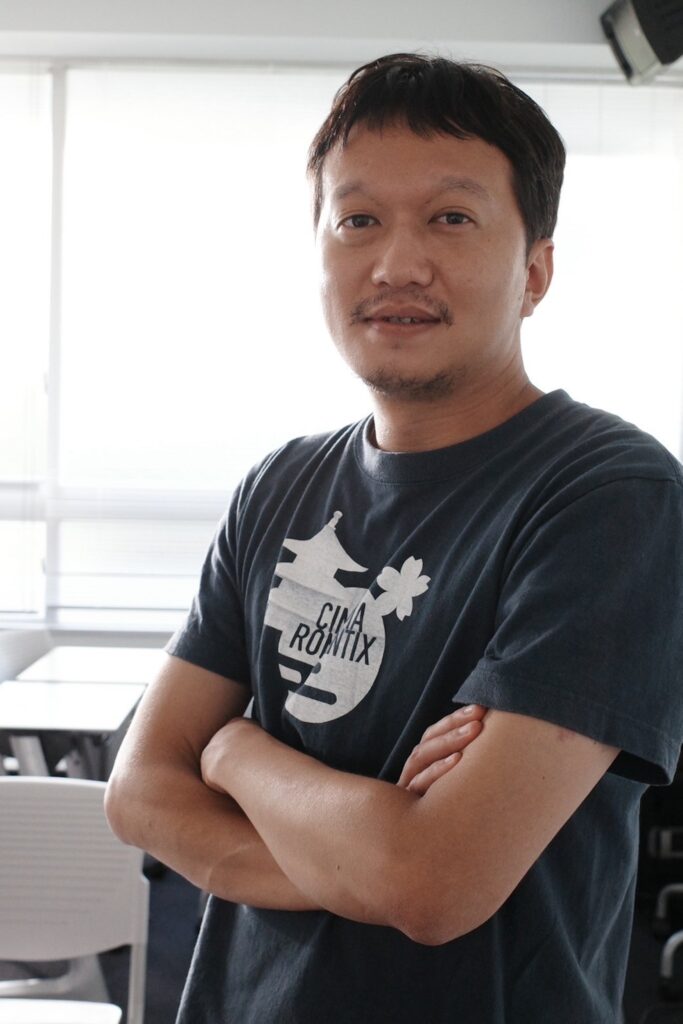


——映画『よそ者の会』の制作経緯を教えて頂けますか?
西崎監督:この作品は、私が大学4年生の時に大学院入試のために作った映画です。大学入学したタイミングでコロナ禍になり、大学に対する思い出が乏しいと4年生になった時に気がついたんです。それで、大学を使って映画を撮ってみようと考え始まったのが、本作でした。
—–ロケ地は、実際に通っていた大学ですね。
西崎監督:実際に通っていた大学を使わせて頂きました。
—–数ある映像作品で、大学をロケ地にするのは商業映画では良く見受けられますが、学生映画や自主映画では珍しいと感じます。
西崎監督:過去には自主映画で大学をロケ地に選んで撮影している作品はあったと思いますが、現代で大学をロケ地にして撮影するのは比較的、難しいのかもしれません。だから、学生映画として使わせて頂けたのは、非常にありがかったです。
——大学をロケ地にする所から始まったと思いますが、なぜ、この物語が生まれたのでしょうか?
西崎監督:最初に、テーマになる軸を決めようと思って、そのタイミングで自分が一番関心があったのが、コミュニケーションの齟齬でした。それから生まれる物語にできるアイディアがないかなと考えた結果、それぞれの出自やバックグラウンドの違うアバランスな人達が、大学に集まって、何かコミュニティを作る話にできないかなと考え、会合を作る話になりました。
—–物語的に、非常に扱うのが難しく、ネタバレも気をつけないといけない一面もあると思います。難しい題材だと思いますが、映画にするにしても、世間一般の日常で話すにしても、話せないタブーの側面もあると私は思います。その点、監督はどうお考えでしょうか?
西崎監督:自分としては、切り込んでいる気持ちは全くないんです。私が大学4年生の時に卒業論文で書いたのが、映画『太陽を盗んだ男』についてだったんです。その作品が、本当に好きな映画だったので、非常に影響を受けています。
—–この映画の制作の話を受けた時、物語や鈴木の人物像をどう捉えましたか?
川野邉さん:元々、西崎監督とは、僕が映画美学校アクターズ10期生として、西崎監督が監督コースの25期生として学内で出会いました。僕達は、それぞれお互いに同期だったんですが、通っていたのが2021年度か2022年度辺りで、その時に初めて監督の短編作品『しどろもどろ』を観させてもらって、その作品はフェイクドキュメンタリーの短編だったんですがとても面白かったんです。自分も昔フィクションコース通っていたんですが、すごい才能のある監督がいると興味を持って、その後、仲良くなったんです。僕自身、シナリオを読ませてもらって、すごい面白く才能があると思っている監督の作品に自分が主演で出演できる事に嬉しかったです。正直、シナリオを読む前から出演オファーを快諾しようと思っていたんです。それでちゃんとシナリオを読んでみたら、内容が非常に面白かったんです。シナリオのセリフやト書が非常に洗練されていて、無駄がないシナリオだったんです。且つ、俳優として演じて、自分の役柄と全然合わない人物や内容が理解できない時、セリフが全然入って来ない時があるんです。結局、現場で間違える事や言い直しも起きる時もありますが、『よそ者の会』に関しては、ほぼ間違える事もなかったんです。それで、どうしてだろうって考えた時、鈴木という人物が自分の体験とリンクするキャラクターでもあったからなのかなと。大学生の時に僕は、一年間休学して、映画美学校に通っていたんですが、復学したら、大学の時の友達は誰もいなくて、割と自分の居場所について悩む時間や気持ちがあったんです。卒業後、社会人をしながら、映画を作っていたんですが、会社員をやりながら映画を作っていると、自分は一体、何者なんだろうと思う瞬間があったんです。働いてはいるけど、土日は映画を作って、本当の自分って一体何なんだろう?という感情が沸き起こっていました。だから、このシナリオに出会えて、とても嬉しかったです。
——川野邊さんが話す疎外感。自分が今、どこに向かっているのか分からない。自分が今、どこに属しているのか分からない感覚は、非常に理解できます。鈴木という人物の疎外感を感じている部分が案外、川野邊さんが感じている感情とマッチングした感じですか?
川野邉さん:その感情は、かなり持っていました。僕は理系の大学に通っていましたが、物語の人物の背景と近いと思う共通点もあり、面白かったです。
—–ある意味、鈴木だけでなく、登場人物の3人に親近感が湧き、少なからず共感性もあると思います。私自身、この作品を観て、「よそ者」について考えるきっかけにもなりました。自分自身もまた、社会の中のよそ者ではないかと思う瞬間があります。だから、この映画の中での「よそ者」と自分自身の中にある「よそ者」が、非常に共感性があると思っています。「よそ者」と感じる瞬間は皆、持っていると思います。では、坂本さんにご質問です。まず、本作の脚本を手にした時のご感想をお聞かせ頂けますか?
坂本さん:純粋に面白いと思い、ワクワクしました。生理を指摘するシーンや大学の同級生とばったり会うシーン等自分も感じたことがある葛藤が描かれていたし、絹子という役に自分とリンクする部分をたくさん感じたので演じることが楽しみだと思いました。爆弾というモチーフがこの物語の中でどう作用していくのだろうと初めて読んだ時はまだ、朧気だった事も覚えています。
——本作の物語は、非常にナイーブな題材だと私は思います。一般に劇場公開するのもギリギリで、タブーな一面もあると思います。なぜ、この題材に取り組もう、挑戦しようと思われたのでしょうか?
西崎監督:映画美学校に入って最初に作った短編にも、爆弾が、作品の肝になっているんです。私自身が、物語で爆弾を使いたがる傾向があるのかもしれないです(笑)。本作においては、爆弾と人の感情、社会への思いが上手くリンクできると思って、このアイテムを入れていました。
—–社会に対する不満や怒り。なぜ、人はここに辿り着くのか?
西崎監督:私自身、この映画の中で出てくる人達が言っているような事を人に対して思っていたりする時があります。高校生の時に頑張って勉強して、いい大学に行って、大学時代にすごく遊んでいたとしても、いい会社に入れる事も全然ありますよね。私は、大学時代すごく頑張っていたけど、遊んでいる人達にどんどん抜かされてしまうのかと、漠然とした将来に対する不安を感じていたんです。持っていたからこそ、余計に自分の周りの人や社会に対して悲観的に物事を見たりする感覚があったと思うんです。
—–少し話が逸れますが、監督が話す事は40代から50代の方が焦燥感を抱えるミッドライフクライシスや20代から30代の方が抱えるクォーターライフクライシスにも似ていると、私は思いました。
西崎監督:これからの人生の事を考えた時に浮かび上がって来る焦りは、通ずるものがあると思います。
—–物静かでありながら、心のどこかに沸々と、社会の恨みや辛みを持つ人はいると思いますが、川野邉さんは鈴木という人物を演じるにあたり、ご自身の中で葛藤や恨みなど何か抵抗はございましたか?
川野邉さん:シナリオを最初に読んだ時、鈴木は自分が演じたいと思ったキャラクターだったんです。どんな人物にしようかと西崎監督とたくさん話し合った記憶があります。たとえば、現場で指示を受けたのは彼の話す速さとトーンでした。監督自身の編集や撮影のリズムがあるので、それを掴む為に鈴木という人物を理解しようと努力しました。撮影は順撮りだったんですが、最初の方は探り探りで演じました。でも、鈴木に近づけば近づく程、社会と断絶する感覚を受けました。どんどん自分が窮屈な世界に閉じこもる圧迫感を感じて、だから爆弾を作るのかも知れないという気持ちも繋がりました。ここから出してくれと、訴える窮屈感はあった気がします。
—–鈴木という架空の人物ですが、彼の心の中に少しずつコンタクトして行った感じですか?
川野邉さん:鈴木は色々な仕事をして来たと思うんです。彼の頑張りが、これまでにもあったと思うんですが、タイミング悪く挫折の経験が多かった人だと思っているんです。それが、社会への憤りに繋がって行く過程があると思います。
—–鈴木の過去が、どうなのか?あれだけでは、思い浮かばないと思います。 なぜ、清掃業という世界に行ったのか。もしかしたら、訳があって、清掃業界に足を踏み入れたと思いますが、鈴木は働いている途中でリストラに近い処遇を受けますよね?彼は自分にも他人にも、正直に生きていると思います。その正直さが、裏目に出ていると言いますか。でも、同じ経験が過去にも何度もあったと仮定した時、人として正直に生きているにも関わらず、すべてが裏目に出てしまい、人生につまづき、社会に不満を抱き、生活面で嫌な思いをたくさんしていると思います。本人自体は、悪くない。悪意を持って、人に接している訳ではないのに、なぜか、悪い方向に行ってしまう。もしかして、彼の背景にあるのではと思います。その点、どうですか?
川野邉さん:彼は、正直で多不器用な生き方をしていると思っています。彼は、うまく生きられない人で、皆みたいに器用に、上手に物事を流せない性格だと思っています。その点は、僕自身も似ている一面があります。だから、その点を自分でどう整理していいか分からずにいるんです。
——あの場面が、40分の中でも一番重要なシーンだと思います。あの場面から鈴木という人物が、ガラッと変わって行く様子を伺えます。物語自体も色が変わって行く特異点だと思います。
川野邉さん:ただ、受け入れるしかない気持ちもあります。その後に家のベッドで寝ている場面がありますが、彼の中でのリアクションが、周囲と一歩ズレているんです。西崎監督とは、彼は世間の犯罪者のようなやばい奴として描かないようにしようと話をした気がします。
西崎監督:確かに、そんな話はしましたね。たとえば「社会不適合者」みたいなラベルで彼を表現するのは違うよね、ということは意識していました。それから、発達障害やADHDといった診断に当てはめてしまうような描き方は避けたい、という話もした記憶があります。鈴木を、何かしらの属性に押し込めるようなことはしたくなかったんです。
川野邉さん:確かに、その点は話し合った気がします。
—–坂本さんが演じる絹子に感情移入した点は、どこでしょうか?
坂本さん:自分がよそ者である事を隠し、周りに迎合しながら生きる姿に共感しました。自分も中学校や高校生の頃、とにかく周りに合わせ、言動の一つ一つを気にし、浮かないために行動や持ち物を選んでいました。いつのまにか自分がどうしたいのかを考える事を忘れてしまい、それを思い出して活き活きとする姿、怒りが込み上げる瞬間等、描かれている絹子の感情の一つ一つが私の中にも存在している感情でした。
——犯罪者にならないと言うより、彼は犯罪者になれないんだと思うんです。どれだけ怒りがあって、爆弾仕掛けて、爆発させたい気持ちがあっても、テロを起こしたい、無差別殺傷事件を起こしたい気持ちがあったとしても、彼にはその勇気がないと思うんです。だから、どこまで行っても鈴木は、犯罪者にはなれない普通の人。そんな人が恐らく、社会にはいっぱいいると思います。その代弁がこの作品であると思います。
西崎監督:たとえば、脚本を書いて面白いと思っても、映像にしてみたら、少し違和感がある時があります。自分で作ろうと思っていた事が、手前まで来た時に思っていたのと違う感覚は、様々な場面であると思うんです。自分の感情が溜まって来て、実際にその状況自体を変えられるようなアイテムも作ってみたけど、作った上で、もう一度冷静になった時、少し違うかもという感覚は、普遍的だと思うんです。

—–この物語の鈴木のように、社会への復讐や報復を抱えて生きる人物は、もしかしたら、この日本のどこかに一般人と紛れて普通に生活しているのかなと私は思いますが、この作品の制作を通して、このような方々の世間の見方や監督自身の中での見方に対して、何か変化はございましたか?
西崎監督:それこそ、今おっしゃっていただいたように、同じような感覚を持っている人はやはり、たくさんいると思うんです。実際、実行してしまった人のニュースもありますが、そんな感覚が蓄積されるのは、それこそ、コミュニティに入れていない環境もあると思うんです。社会から相手にされず、社会が用意したレールに乗れず、そんな人達がたくさんいると思うんです。その行動を引き留める事ができるのは結局、人と人との繋がりじゃないかなと思っているんです。絹子と槙生が出会い話す事によって、新たな場所を得られ、心の中に抱えている爆弾を引き止める存在が欲しいと思うんです。間接的な繋がりが色んな場所で欲しいんじゃないかなと思いました。
——今のお話をお聞きして、私は映画を観て思っていたのは、爆弾は物理的なものと認識していましたが、鈴木自身が持っているのは、危険物の爆弾ではなく、本当は心の爆弾を抱えて、生きているのでしょうか?
西崎監督:その解釈こそが、一番大きいと思います。
—–そんな方を救う訳ではないですが、心の爆弾を持っている人は大なり小なり関わらず、皆さん持っていると思うんですが、それを救うにはどうすれば良いでしょうか?
西崎監督:爆弾を抱えている事自体は、全然悪い事ではないと思っています。皆、抱えていると思います。そ西崎監督:爆弾を抱えている事自体は、全然悪い事ではないと思っています。皆、抱えていると思います。その爆弾を完全に失くす事はできないと思うんです。それを爆発させないでいる為の何かしらの抑制が欲しいんだろうと思います。その抑制する何かは、多分、人によって違うと思うんですが、社会との繋がりや人との繋がりがちゃんと、それぞれの人にあったらいいんじゃないかなと思います。
—–先ほどお話されたコミュニティやそれぞれの居場所が大切ですね。鈴木という人物が何を思って、何を感じて生きているのか。川野邉さんは演じながら、彼の中にある感情をどう受け止めていましたか?
川野邉さん:割と最初は、鈴木という人物を掴まえるようにして、演じなきゃと意識して演じていたんです。だから、彼は何を考えているか分からなかったんです。こんな行動をするのかと現場でも監督と話し合いながら演じさせてもらったんですが、まだ掴めない事が多々あったんです。最終的に、映画を撮り終わる時まで完全には掴み切れない人物。でも、分からないものを観客の方にも一緒に感じられるのが一番いいんじゃないかなと思っています。分からないをそのまま観客の方に考えながら見観てもらうのがいいと思って来たんです。最後の撮影では、深くは考えず、鈴木の感情のまま、演じるように意識しました。最近の日本映画では、考えながら観させられる作品が少なくなって来たように感じています。分かりやすさが優先になってしまっているので、考えてもらいながら観てもらえるのは、作品の魅力の一つだと思って演じています。
—–「よそ者の会」をどう捉えてインプットし、どうアウトプットされましたか?
坂本さん:まず私は、絹子が自分の居場所を見つけるために立ち上げた会なのだと思いました。誰かの話を聴き、その相談に乗る事で絹子自身が救われていたのだと思います。そうして鈴木と出会うまで自分の心や現状から目を背けていたのだと思いました。絹子の人の為になりたい欲求と、自分自身が本当は何を考えているのかよく分からず葛藤している心のぶれ、そこから抜け出していく変化を表現できたらと思いながら演じました。
——鈴木のように少し過激に世間を生きている人も少なからずいるのかなと、私は思います。現に、過去には実際の社会で安倍元首相にテロ行為を行った男性も、日本人の中には現実にいるのも確かだと思います。一定数、反社会的な人が生まれてしまう事実はあると思いますが、そんな人物を生まないために、今、日本社会で生きている私達は、何をすればいいと思います?
川野邉さん:ちょうど、大阪万博の会場で爆弾を持っていると、嘘の発言をしたニュースが今、話題になりましたね。爆弾系の事件は、日常生活の中で起こる事だと実感しました。
—–傍観者的な立場ですね。それも、非常に大切な事だと思います。すべては起こるべくして起こっていると思います。一人の人間の力で止める事はできないと思います。起きた後、どうするかと思います。事件が起きて、それを受け流すのではなく、なぜ起きたのか?と、ちゃんと一人一人が向き合って咀嚼しないと、必ず同じような人物は産まれます。同じ事件が、必ず発生すると思います。それを止める事はできなくても、少しでも相手に歩み寄る事も大切だと思う事もあります。
川野邉さん:コミュニティが狭い中で、起きたしまった悲しい事件ってたくさんありますよね。
—–坂本さんは、どうでしょうか?
坂本さん:自分も含め誰もがよそ者であるということを全員が自覚することだと思います。誰もがよそ者であることを理解し、干渉しすぎず尊重し合う。そうすればもう少し生きやすくなると思います。
—–コミュニティを通して、その方を救えたかもしれませんが、それはもう起きてしまった事。救えたかもと言っても、それは遅い話かもしれませんが…。家庭の中でトラブルが起きている時、外側の人間がコミュニティを作って、交流する事が大切だと思います。そんな人間を一人でも減らす、増やさない事が大切ですね。監督は、どうでしょうか?
西崎監督:今のお話を聞いていて、頷ける事もありました。今、生きている人の中には、本当に大変な状況にいる人がたくさんいると思うんです。事件が起きてからじゃないと改善できないような社会も含めて、たくさん問題はあると思います。プライベートでの家族の話もそうです。世の中には解決できない問題がたくさんあるので、まずは現状理解を進める事が、第一歩だと思います。
—–それを私は、映画で実現できるのではないかと、強く信じています。映画という上映する場が、人々が集まるコミュニティで何かできないかと願いたいです。
西崎監督:映画を通して、人と場所を繋げて行ける場ができればいいなと思います。
—–それぞれの立場や肩書きといった垣根は関係なく、皆さんで一緒に人として取り組めたら、社会はもっと明るい方向に進んで行くと信じたいですね。今の日本社会は、特に疎外感を感じている方が、世代を問わず、たくさんいるのでは?と、私は感じますが、誰もが孤独と感じる感情を表に出せない社会ではと感じていますが、もし目の前に、そんな方がおられたら、3人はどう接しますか?
西崎監督:簡単に、相手の事を擁護する事は難しいと思います。結局、言葉で歩み寄ったとしても、何か状況が改善するかどうかは、正直分かりません。少なくとも、何かしらの言動を起こして、手を差し伸べられるような人でありたいと思いますが、具体的にどうすればいいのか、答えは見つかっていません。
川野邉さん:手を差し伸べるのは、非常に難しいと感じていて、たとえば、自殺願望や人生の疲労感を持っている人に手を差し伸べるのは、とても難しいと思います。たとえ、それが友達だったとしても。電車の中で急に怒ったりする人を止めるのだって、大人になればなるほど難しい気がします。西崎監督が話しているコミュニティを作る事は、とても大事な事だと思うんです。視界が閉ざされてしまうと、人は追われてしまうのではないと思います。コロナ禍でそれを一番感じました。映画『よそ者の会』は、コロナ禍だからこそ作られた作品であり、コロナ禍を経験した人が物語る説得力を感じています。
—–もう一度、あのコロナ禍が何だったのかと再認識できます。過去に立ち帰った時に、コロナになった結果、自分達の環境がどうなったのかを、もう1度、考えるきっかけになっていると思います。
川野邉さん:コミュニケーションの阻害は、コミュニティの中の人と交流する事によって、乗り越えられると信じています。
—–コミュニティやコミュニケーションの大切さを再認識させられます。人は、一人だと生きていけないと思います。監督は、どうでしょうか?
西崎監督:全然、答えが出せなかったんですが、人は人とじゃないと生きていけないという話もありましたが、私も一人のよそ者として、違うよそ者と寄り添うぐらいの事はできます。よそ者はよそ者といたら、その瞬間だけでも、よそ者じゃなくなります。そんな歩み寄りはできるのかと思いました。
—–坂本さんは、どうでしょうか?
坂本さん:私は、自分から声をかけるかどうかは分かりません。ただ、その人を注意深く観察し、助けを必要としていた時にいつでも手を差し出せるように見守りたいです。自分の事を見ている人が少しでもいる事を忘れず、そういう存在を自覚している事が大切だと思います。
——最後に、映画『よそ者の会』が今回の上映を通して、広がって欲しい、伝わって欲しいなど、何かございますか?
西崎監督:この作品の題材は、すべての人に開かれた映画というより、本当にミニマムな印象を受けると思います。もしかしたら、入り口が狭いのかもしれないと、今宣伝活動をしながら感じています。ですが、本当に多くの方に作品が広まってくれたら、嬉しく思います。生きていれば、様々なコミュニティに所属してます。たとえば、人間というコミュニティにも。もっと小さい単位で言えば、家族や部活、会社など。そして色々なコミュニティの中に色々な自分がいると思うんです。その中で、それぞれの自分との乖離が生じ、そこでの乖離が、疎外感やよそ者という感覚に繋がっているのだと思います。よそ者という感覚は多分、どの方にも存在していると思います。ぜひ、たくさんの方々に観ていただけたらと思います。
——貴重なお話、ありがとうございました。

映画『よそ者の会』は現在、5月23日(金)より東京のテアトル新宿にて、上映中。また、6月24日(火)には大阪のテアトル梅田にて、上映予定。
