衰え行く地方都市を舞台にした映画『ナマズのいた夏』中川究矢監督インタビュー
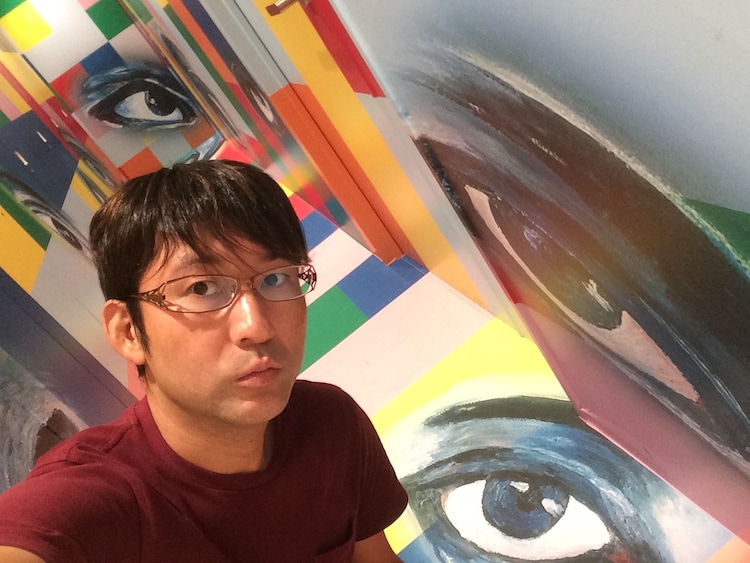


—–最初に、映画『ナマズのいた夏』の制作経緯を教えて頂きますか?
中川監督:前回『あ・く・あ~ふたりだけの部屋~』という映画を作った時、配信や音楽プロデュースをしてくれたFabtoneInc.という会社があるんですが、その会社の宮西プロデューサーと一緒に映画を作ろうという話になって、比較的自由にやらせてもらった映画です。関東の片田舎を舞台に映画を撮りたいと、ここ数年ずっと考えて来たのと青春映画をちゃんと撮ったことがなかったので、やってみようと。長編の青春映画を関東の田舎町を舞台に撮ってみようと思い動き始めました。数年前から僕は、狩猟採集系のYoutubeチャンネルをやっているんですが、それで「アメリカナマズ」の存在を知りまして、この生物の存在が面白いと思ったんです。特定外来生物に指定されていて、日本の生態系にとっては、厄介ものの魚の部類に入るんです。魚本人は一生懸命生きているだけなのに、厄介者扱いされているんです。アメリカナマズは、どこにでもいる生物ではなくて、特に、霞ヶ浦水系(※1)や印旛沼水系(※2)の千葉県や茨城県一帯に生息繁殖しています。アメリカナマズがいる場所をメインの舞台にすれば東京に住む若者達が都会と田舎の街を行ったり来たりする姿を描けるなと思いました。また、物語の中で釣りが人を呼び寄せていますので、この物語にとって、ナマズを釣る行為が様々な意味で人々をまとめてくれる存在になっています。技能実習生の問題も描きたいと思っていましたので、色んな要素を織り交ぜながら、アメリカナマズという存在のイメージが物語をまとめてくれて、今回の映画に仕上がりました。
—–ナマズを通して、様々な人を呼び寄せる物語なんですね。
中川監督:映画のアイディアもナマズが呼び寄せてくれました。
—–今まで、ナマズを主体にした映画は聞いた事ないと思いました。日本映画の『うなぎ』という有名なタイトルはありますが、ナマズはなかなか聞いた事ないと思って、非常に斬新だと思っていました。
中川監督:小さい頃からナマズが、好きだったんです。昔からナマズの絵やキャラクターグッズに惹かれていたんです。ナマズの浮世絵をFacebokの壁紙にずっとしていました。
—–幼い頃からナマズと深い縁が、おありだったのですね。
中川監督:ナマズに対しては、ビジュアル的にすごく親しみを覚えていました。

—–外来種のナマズと地方都市の故郷に帰って来た幼馴染の3人。この2つには、ある種、逆説的な関係性が描かれているのかなと私は感じましたが、今の若者が抱える生きづらさを表現していると思えました。その点、どうでしょうか?
中川監督:映画の中では、ベトナム人の技能実習生が出ていますよね。彼らは海外から来ている方々ですが、映画の中ではパワハラを受け、労働時間搾取を受けている存在です。ナマズは生物の世界では、生命力が強すぎて、日本の在来種を減らす強い存在で、その点は対比的に描いていています。あと、ナマズは濁った水の中にいるので、普段目には滅多に見えない生物です。目に見えないもの、可視化できない心の中の存在という表現もしています。若者達が、自身の心の中にある見えない問題が徐々に浮き彫りになって来る象徴でもあります。
—–外来種のナマズ、地元に住んでいたけど一旦外に出て帰って来た若者達、海外から日本に来た技能実習生。みんな外から来ている存在で、外から来ているが、何かしらの妨害があり、差別や偏見を受けている。逆説的でもありますが、実は強い繋がりや関係性があると私は受け取る事ができますが、その点はどうお考えでしょうか?
中川監督:回遊魚みたいに世界を旅する訳ではないですが、魚だからどこから来たのかははっきり分からない。もしかしたら、けっこう遠くから来たかもしれない。その何とも言えない浮遊感がいいと思いました。アメリカナマズのいる場所を中心に上京した田舎の若者や海外から来た技能実習生が出入りする姿を通して、地域で起こった物語を描くのがいいと思いました。

—–ナマズを比喩にして、若者や技能実習生の心の痛みや社会に対する相反する思いを、ナマズを通して見えて来ると思います。地方都市から見て、外から来た種は、よそ者扱いだと思います。一度、地元を離れた若者達も同じ扱いになると私は思うんです。現実問題、私自身も地元を12年間離れて、5年前に帰って来て、全然知り合いも一人もいない状況における環境が非常に似ていると思えました。一度、家を出た者が、どうしても馴染めない部分もあるなと私は思えます。よそ者でもありますが、それでも、その土地の人間として認められるには、どうすればいいと思いますか?
中川監督:それは、自分で頑張っても限界のある事かもしれませんが、この物語のラストで主人公の達生が、今まで関わる気がなかった自分の父親の工場に対して、少し積極的に関わろうと心の変化が起きます。結局、関係ないとゼロにしてしまうと、本当に繋がりがなくなってしまうと思うから、そこは100じゃなくても、0と100の間を探って行くしかないかなと思います。だからもう、「俺、東京出ていたから関係ない」では地元の繋がりや関係性が薄れてしまうと思うんです。少しでも何かに関わろうと、自分から動く事が大切だと思います。
—–今の私の心情と重ねて、心にグサッと来ました。
中川監督:無理に関われと言われても、無理だと思うんです。僕自身、地元は京都ですが、いまはほとんど関わってないです。
—–率直に言えば、映画の世界はすべて、東京のイメージが強いと思います。だから、成功や知名度を考えたら、東京に比べたら関西にはチャンスは少ないと思うんです。
中川監督:今は東京一極集中になっていますね。

—–ただ東京一極に集中でなくても、活動できると思って関西に拠点を置かせてもらって活動しています。東京の意識も大切ですが、地元を大切にする気持ちもちゃんと持ちたいと考えています。今、生きづらさを抱えて生きているのは、この映画に登場する人物だけではないと思います。この現実社会でも、生きづらさを感じている方々はたくさんいると思うんですが、何に対して生きづらいと感じていると思いますか?
中川監督:一言で説明するのは難しいですが、まず社会に元気がない点、大人達に元気がない、年長者達の元気がない状態で、この社会を元気に生きて行こうとは、中々思いにくかも知れません。その点は、一つあると思います。大人達が、子ども達にこの国の未来を示せていない事が問題だと思います。20代までの若者達に対して、30代以上の大人達がよい未来を示せていないのが、根本的な問題としてあると思います。
—–人から聞くのは、今の若者達が、今の日本自体が「オワコン(終わったコンテンツ)」だと。だったら、もう海外進出して、就職した方がまだいい方と。
中川監督:日本人がオーストラリアやカナダに出稼ぎに行くのは、90年代では考えられなかった事ですよね。海外の方が遥かに時給が高いから、海外に出る人は出て行くと思うんです。
—–もっと、若者にチャンスを与える国になって欲しいと思うんです。
中川監督:経済的に苦しい社会だと、子どもも簡単には産めなかったり、経済的な事は大きいと思います。架乃ゆらさん演じるヒロインの結衣もまた、高校中退でしばらくバイトをしていたけど、風俗の世界に流れ着く背景には、単純に収入が良いからという要素はあると思います。
—–現実でもある話ですね。
中川監督:世界の国で調べたデータによると、社会参加意識が低い国は幸福度も低いというデータがあるんです。日本は低いんですね。それがまた、より閉塞感に繋がっているんだと思います。政治的な発言も嫌煙されがちで、気軽に話し合われてないのが現状ですよね。日本の社会参加意識が低くて、抑圧されている点は、より一層に暗さを与えて、生きづらさに繋がっている一面もあるんじゃないかという気はします。
—–政治に関わらず、社会の話をするとダサいと言われる風潮もありますが、果たして、それでいいのか?
中川監督:慎重に考えないといけない問題だと思うんです。関西でノリとして、社会のあれこれを話し合うのがダサい。「何、真面目に考えてるねん」という空気感がありますが、「いや、それ真面目に考えなきゃいけない問題やろ」と思う時があります。だから、アジテーションが過激な政党が躍進しちゃう一因にもなっていると思うんです。
—–若者の陽キャみたいなノリでやっちゃっている雰囲気はあると思います。
中川監督:「ぶっ壊せ、改革や」という軽いノリの表現が、ある程度、受け入れられてしまうのは、関西の悪い側面だと思います。お笑いの世界の影響もあって、90年代に入ってから、真面目に頑張っている奴を直ぐにあざけ笑うような時代の空気になったところがあって、それは嫌だなと思いながら京都で過ごしていました。今、日本の社会は元気じゃないので、特に慎重に考えるのが大事な時期だと思うんです。
—–原因は分かりませんが、一つは9.11以降の世の中の価値観がガラッと変わったと私は思います。あの時期から世界的に経済が変わり、その次にリーマンショックが起きて、人々の意識や価値観に変化が起きたと思うんです。
中川監督:でも、アメリカが一時、圧倒的に強い国というイメージがあり、そのアメリカに付随する日本も元気だったから、お互いブイブイ言わせていた雰囲気が9.11以降、アメリカには様々な問題があると日本も気づいたし、アメリカ以外の国が思い出した頃だと思います。日本はアメリカに対して、対米従属なので、その影響も受けていると思います。
—–経済に活気が溢れれば、人々の活気が溢れるのは当たり前であり、それは比例しています。経済が悪くなれば、生活水準も悪くなるのも当然の事ですよね。それをどうしたらいいでしょう?個人の力では、到底及ばない事だと思います。
中川監督:まずは、色んな背景を知ろうとして行く事はした方がいいと思います。考える事を放棄しちゃうと、より視野の狭い人間になっちゃって、外国人差別に走ってしまう人もいると思います。何々人はダメだみたいな考え方は、簡単だと思うんです。深く考えずに排除できてしまうので。色んな背景を知った上で、より良い社会を作って行こうという意識が高まって行く事が大事だと思っています。

—–若者に限らず、今をどう生きようかと考えて悩んでいる人は、本当に大勢いると思うんです。若い子だけじゃなくて、シニア世代や中間世代も含め、本作が生きるヒント、また何かの導きになるんじゃないかと私は思います。その導きになるものがあるとすれば、それは何だと思いますか?
中川監督:僕は、一歩踏み出す事だと思っています。企画書には、「若者よ、絶望せよ」と書いていたんですが、若いうちはどうしても何かにぶつかったり、何かを抱えている心の問題に向き合おうとしていると思います。ほとんどの場合、壁にぶち当たってしまうと思うんですが、それを避けていたら、人は成長しないと思いますので、それがネガティブな結果を生んだとしても、前向きに何かに向き合い、好きな子にアタックする事も同じだと思います。傷つく可能性も高いけど、それでも、長い目で見たら人生を素敵にしてくれる存在になると思うんです。たとえ傷ついたとしても、それはいい事なんだと、この映画で伝えたい部分はあります。
—–傷つく事は、あらゆる場面でたくさんありますよね。
中川監督:たとえば、恋愛しない若者が増えていると言われていますよね。でも多分、うまく行くと分かっていたら、みんな恋愛するんですよ。自分のペースを乱されるのが嫌で、みんな避けている一面はあると思うんです。家でネットの配信を観ていたら、快適に過ごせると思うんです。でも、恋愛は基本的に自分のペースを乱されるものであって、ぶつかって砕けるのが当たり前だと思います。どんどんぶつかって、傷つく結果になったとしても、トータルの人生で見た時に、絶対にそっちの方が楽しい事を伝えたいですね。

—–人生経験が、増えますよね。現在、慎重派が増えてしまったんですね。ただ、今の社会が人生を経験したいと思わせない社会になっていると思うんです。冒険して、当たって砕けて経験して、それが楽しいという価値観があると思いますが、努力や苦労も嫌われますね。でも、その泥臭さがいいと思うんです。恐らく、私達大人が人生を冒険しながら、これが楽しい事だともっと示していかないと、これからの若い世代が何をしても面白くないと答えを出してしまうと思います。
中川監督:経済や社会が停滞している状況で、新しいポジティブなものを若者に提供できないまま、今現在、社会が進んでいる危機感は感じています。
—–世の中を俯瞰的に冷めた目で見ていると思います。そういう世の中、寂しく感じますね。
中川監督:折角、東京でオリンピックを開催しても、盛り上がらずに不正やキャンセルカルチャーもあって、スキャンダルだらけのオリンピックでしたよね。
—–それを言えば、大阪万博もまた、まさにめちゃくちゃですね。逆の意味で、盛り上がってしまっていますね。
中川監督:今は、非常に難しい時代だと思うんです。このインターネットが普及してからの時代の変化は、物凄い速度だから、感性がどうしても分離しちゃっている影響はあると思います。よく話すのが、僕の世代が好きな女の子に連絡を取るために、その子の家に電話してお父さんが出てドキドキした最後の世代だと思うんです。僕より後の世代は、思春期の時に携帯電話があったので、電話口にお父さんが出てドキドキする事はないんです。これは、結構、大きな感性の変化だと思います。
—–そのドキドキ感を味わえなくなった世代が、増えてしまいましたね。私の世代になれば、学生時代の頃には既に携帯電話を持っていたから、そのドキドキ感を感じた事はないと思うんです。
中川監督:それが、さらに今ではLINEやSNSで、もっと気軽にみんなと連絡先を交換して、誰でも気軽に連絡を取れる時代ですよね。それに限らず、感性の違いは各世代間でそれぞれにあると思います。
—–ネットやデジタルの発達によって、人との距離感は近くなりましたが、その分、感情面は希薄になっているのかなと思います。
中川監督:気軽にコミュニケーションしやすくなった分、相手の事を深く考える時間が少なくなっているのはあると思います。総括すると、色々な状況があって、それぞれの登場人物が深く考えざるを得ないような状況にしたのが、この映画『ナマズのいた夏』です。
—–最後に、映画『ナマズのいた夏』が、今回の上映を通して、どう広がって欲しいなど、何かございますか?
中川監督:分かりやすいハッピーエンドや過激な描写のある映画ではないんですが、最近、本作のような青春映画は少なかったと思うので、じわじわ広がってくれたら嬉しいなと思います。派手な映画ではないので、爆発的な盛り上がり方はしないと思うんですが、届くべき人にじわじわ広がって届いてくれると嬉しいと思います。
—–貴重なお話、ありがとうございました。

映画『ナマズのいた夏』は今後、5月16日(金)より栃木県の宇都宮ヒカリ座にて上映予定。また、山口県の萩ツインシネマは近日公開予定。
(※1)恵みの湖霞ヶ浦https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0302_kasumi/0302_kasumi_00.html(2025年4月4日)
(※2)【水路を航く】#11/千葉県・印旛沼水系①因幡捷水路https://www.kazionline.com/articles/suiro11(2025年4月4日)