本格的なゴスペル音楽映画『雨ニモマケズ』飯塚冬酒監督インタビュー



—–まず初めに、映画『雨ニモマケズ』の制作経緯を教えて頂けますか?
飯塚監督:僕は18年ほど前にゴスペル音楽と出会い、以来ゴスペルのイベントをプロデュースしたり、ゴスペルのドキュメンタリーを2本ほど制作をして来たのですが、いつかフィクションとしてのゴスペル映画を作創りたい想いはずっとありました。いろいろなタイミングも重なり、今回、ゴスペルをテーマにした映画『雨ニモマケズ』という作品の制作に至ることになりました
—–本作が公開されるまでに、山を越え、谷を越えて、ここまでの制作が許されたんですね。
飯塚監督:「山を越え、谷を越え」たり「制作を許さ」れるということはあまりなかったのですが、最も近しい人が亡くなったことが映画を撮る一番大きな動機だったような気がします。今、映画を撮らないといつまでも創れないんじゃないかという想いに後押しされたという感じです。
—–少し違うかもしれませんが、ある意味、追悼の想いもあるのでしょうか?
飯塚監督:追悼の想い、その方の死を悲しむのは当然ですが、それ以上に考えたのは、果たして、僕が死んだ時、何をみんなに残せるだろうと、いうことでしょうか。僕の人生も50年を超えているので、何かを残す方になると思うんですね。「残せるもの」も作品の根底に据えながら脚本を書いていました。
—–今のお話をお聞きして、この映画を制作した事が、監督自身が約束を果たせたのでは?何か発信できるものを、この映画を通して成し遂げたのでは?と感じ取る事できましたが、その点、どうでしょうか?
飯塚監督:映画に限らず、創作物は発信側の者と受け取る側の者があると思うので、どのように受け取って頂いても、それは受け取る側の方の想いなので、私はどんな受け取り方でも嬉しく思います。
—–私は、本作の完成が結実したと感じます。この作品を通して、飯塚監督のゴスペルの活動からここで今、終着点ではないですが、一つの結実として、この映画が誕生したと、私は受け取りました。
飯塚監督:ありがとうございます。本作は僕が18年ゴスペル音楽に携わってきた中で生まれた作品ですが、おっしゃるように終着点ではありません。またおっしゃるように、ゴスペルのいろはもわからない時から親身にそして厳しくご指導いただいた亀淵友香先生や松谷麗王先生からいただいた想いが結実した作品なのかもしれません。東ちづるさんが演じた人物の役名の増渕麗はお二人からいただいたお名前です。

—–タイトルの「雨ニモマケズ」は、日本を代表する詩人の宮沢賢治の代表作をモチーフにしていますが、本作の物語と宮沢自身が詩の中で表現した不屈の精神が、どう化学反応を起こしていると思いますか?
飯塚監督:残されたタツヤは、彼の特性上、おそらく独りでは上手に世の中を生きていくのが難しいと思います。生きづらい彼が自分の中にある想い、宮沢賢治の詩の中にようにこんな風に生きて行きたいという彼の想いも込めているんです。
—–「雨ニモマケズ」。今の若い子達は、努力をしたがらない。努力を嫌う風潮があると思いますが、どうしても不屈の精神という考えに対して、心を動かされない部分もあるのかなと思います。努力を嫌煙する若い子たちに向けて、「雨ニモマケズ」という思想がまた、何か作用するものがあるのかなと、私は思います。
飯塚監督:映画として、少しでも観る人の心に届くものがあれば嬉しい限りです。僕としては、あの詩は時代を超えても、どの時代に行っても、人の本質を描いているような詩だと思います。忘れたころに改めて読むと心新に人生に立ち向かえる、そんな勇気を与えてくれる詩だと思います。
—–露骨に、宮沢賢治のその時の想いが、詩の中で溢れていますよね。
飯塚監督:実は、宮沢賢治は、信心深い仏教徒なんですね。この詩のモデルとなる人物は、斎藤宗次郎と言われています。斎藤宗次郎は敬虔なクリスチャンなんです。仏教徒の宮沢がこんな人になりたいと書いたモデルがクリスチャン。宗教の垣根を越えて人の生き方を賛美している。この詩は、日本の今のゴスペルを象徴をもしているようで映画の中で起用しましたゴスペル音楽は元々、アメリカの黒人教会を母体に生まれた宗教音楽です。アメリカをはじめ諸外国ではクリスチャンの人が歌っています。キリスト教でない人、ノンクリスチャンは全く歌わない。ところが日本では、ゴスペルを歌う9割はノンクリスチャン、キリスト教徒ではないんです。仏教徒、無宗教、関係ない。
—–宮沢賢治自身のバックグラウンド、ゴスペルの世界にも同じように背景がある。
飯塚監督:正しく生きる、ということには宗教は関係ないという宮沢の想いと、歌に宗教は関係ないという日本のゴスペル、そこに共通点を感じていただけるととうれしいです。

—–飯塚監督はゴスペルをライフワークにされ、長年、携わっておられますね。日本の映画でゴスペルを題材にしている作品は、聞かれないと私は思ったんですが、ゴスペルを映画の題材にする事によって、ゴスペルが持つ力はどう、映画とゴスペルの両方に力が作用していると、何かございますか?
飯塚監督:日本でもゴスペル曲を使った映画は今までにありますが、『ゴスペル音楽映画』と謳った映画はありません。そういった意味では『日本初のゴスペル音楽映画』ということになるのでしょう。音楽としても魅力あるゴスペル音楽がもっと日本の映画でも起用されるようになればとも思います。また本作は興行的にいうとミニシアター映画ファンはもとよりゴスペル周辺の方々が多く来ていただいています。ほんの僅かですが、ミニシアターに縁のなかった人たちがミニシアターに足を運んでいただけるきっかけになるようでしたら嬉しいです。

—–映画的なお話をすると、本作は「グランドホテル形式」を採用しており、尚且つ、作品の要素全体で言えば、80年代の洋画を連想させて、映画『コーラスライン』や『フェーム』にも似ている部分はあると感じました。群像劇が引き起こす人間関係は、私たちに何を与える存在でしょうか?
飯塚監督:多くの映画には起承転結があったり、主人公を追って行く物語が多いと思うんですが、その場を切り取った時には、5人の人がいれば、5人のストーリーがあると思うんです。その切り取った一瞬の中の5人や10人、20人のストーリーや人生を描き出すことが群像劇の魅力だと思います。少し質問の答えになってないかもしれませんが多くの人生では大きな事件が起こることはまれだと思います。日常のなか人々が交差していく。交差する一瞬や一日や一週間などで出会った人々が人生に影響を与えていく。僕自身は深く掘る物語や一人の心の底根や大きな事件ではなく交差して行く人生に興味がありますし、そんな映画を創りたいと思っています。
—–だから、一人の人生ではありますが、一歩、社会に出てみたら、色々なたくさんの人がいて、多くの人々と交わる事によって、人の人生が生まれて行くと私は思います。それが、群像劇ではありますが、結局、人は一人ではなく、自分自身は一人の人生を生きていると錯覚しがちですが、他者と交わってこそ、自分の人生が潤うのかなと私は今、考えています。
塚監督:そうですね。僕に作品を創る力が備わったときにもっともっと人の人生が潤って行く姿を掘り下げた作品にも挑戦していきたいと思います。

—–人と1対1で交わった瞬間、化学反応や変化を起こして、何かが生まれると思うんです。一人で考える事もできますが、人と対話した時に全然違う答えが返って来たり、会話が全然違う筋道に行ってしまう。でも、また新しい出会いがあり、新しい学びがあり、多分、人は一人でも生きて行けますが、他人と出会う事によって、人生にはもっと違う選択肢が生まれると思います。
飯塚監督:多分、今までと違う方と会い、知らない人とも会い、考え方の違う人と会う事は、非常に刺激になります。この年になっても、まだまだ考え方が変えられるんだなと、その時その時に思いますね。
—–時には一人でゆっくりしたい時もありますが、もっと人と交わりたいと思いますし、新しい人と出会いたいと思う時もあります。また、その新しい人と出会いから、今まで出会った方とお繋ぎしたいと思います。人の輪が広がる事によって、可能性がいっぱい広がって行くと思うんです。人生の可能性や活動の可能性。人は、一人では生きられなくて、群像劇のある日常で10人、100人いる中の一人かもしれないですが、その集合体が初めて、一つになった時、自分たち一人一人の人生が、もっと輝くのかなと私は思います。
飯塚監督:その通りだとおもいます。
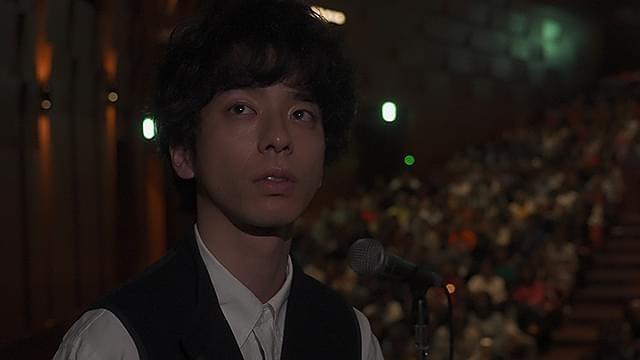
—–作品はゴスペルと人生、映画と音楽、何重にも折り重なり、重厚なものになっていると思いますが、ゴスペルを通して、描かれる人生とは何でしょうか?
飯塚監督:日本でゴスペルを歌う人たちを多く見ていると、ゴスペルに神の存在は関係なく歌っている人が多いように感じます。歌うことが好きな人、みんなで集まることが好きな人、日本ではさまざまな動機でゴスペルに触れる人が多いのですが、中にはゴスペルで救われたという人も多くいらっしゃいます。社会で生きづらかったり、職場や学校、家庭でうまくいかない、そんな方がゴスペルに触れ歌い、ほんのちょっとだけ前向きになれる。ゴスペルは合唱やカラオケは違う何かあるのかもしれません。

—–ゴスペルを深く触れてはいませんが、音楽自体、何でも聞くようにしています。ゴスペルをどこかで流れて来ると、耳に入って来ると思うんです。映画の中でも、特に洋画の場合、時々、ゴスペルが流れて来ますが、それを耳にすると魂が震えて来るんです。だから、ゴスペルには何か人の心の中を動かすものがあるのかなと私は思います。
飯塚監督:ゴスペルの成り立は弱者の音楽から生まれています。苦しい人生を前向きに生きる、そんな黒人奴隷の中から生まれた音楽なので歌う人、聴く人に力を与えるのかもしれません。
—–最後に映画『雨ニモマケズ』が今回の関西での上映を通して、どう広がって欲しいなど、何かございますか?
飯塚監督:多くの人に観ていただきたい、ということを多くの映画製作者は言いますが、その考えであればミニシアター上映という手法をとる必要はないと思っています。ミニシアターに来る限られた観客の中で、この作品に出逢いほんのちょっとだけ人生に影響を与えられる、もしかしたらその観客がほかの人の人生に影響を与えられる、そんな広がり方を目指すのがインディペンデント映画をミニシアターで上映する意義だと思っています。
—–貴重なお話、ありがとうございました。

映画『雨ニモマケズ』は現在、関西では4月19日(土)より大阪府のシネ・ヌーヴォにて上映中。兵庫県の5月10日(土)より元町映画館にて上映予定。